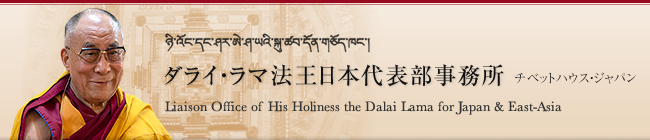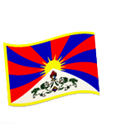チベット亡命政権 情報・国際関係省著「チベット入門」より抜粋
18世紀の末以降、イギリスはチベットとの通商にますます強い関心を寄せるようになった。以前はラサと強く結びついていたヒマラヤの小国たちが、条約や協定などを通じてことごとく英領インドに従っていく状況を見て、チベットは、イギリスが言い寄るに任(まか)せれば、やがては自分たちも近隣国の二の舞になると心配した。そこでダライ・ラマ13世は独立を貫徹した。この政策は、何よりもロシアの南下を恐れていたイギリスを苛立たせた。チベットがロシアの手中に収まることになれば、中央アジアの勢力バランスが崩れてしまう。
チベットとの有効な話し合いの場がもてずにいたイギリスは、清に近づいた。清に対して、チベットが協調的な態度を取るよう協力してほしいと願い出たのである。イギリスのこの努力は実を結び、チベットに関する条約を盛り込んだ条約が、1890年と1893年の2度にわたり、チベットの知らない間に英清間で取り交わされた。
チベット政府はこれを中国の越権行為だとして拒否したため、1903年には英国軍の侵攻を招くことになる。清はもはやチベットに援軍を派遣することもなく、アンバンのユタイが以前警告したように、チベットが独自に行った判断については、清が責任を負う筋合いはないとした。翌年、イギリスはチベット政府と双務的なラサ条約を結び、英軍は1年も経たずにラサから引き上げた。
ラサ条約の規定は、内政外交の両面にわたり、必然的にチベットの主権を前提としていた。そうでなければ、イギリスが条約に書かれた権限をチベットから委譲してもらうことなどできないはずである。ラサ条約にはチベットと清の独自な関係についての言及がなく、それが結果的に、チベットを条約締結能力のある国として認めたことになった。
[一方、ラサ条約で実質的にチベットの主催を認めたイギリスは、同時に清の取り込みにも力を注ぎ]1906年、清を味方に付ける努力が実り、イギリスは清との間に北京条約を締結した。このとき、チベットはまたもや蚊帳の外だった。この北京条約と1907年の英露協商[チベットに関するイギリスとロシアの協定]では、イギリスがチベットで活動することが一定限度認められ、他方ではチベットに対する清の「宗主権」が承認された。
しかしこういった内容は、チベットにとっても清にとっても受け入れがたいことだった。
1908年、清がチベットにふたたぴ軍を進めると、イギリスはチベットとの通商に関して清と英清条約を結びなおした。なお、このときチベットは、独立国として参加することができなかった。
イギリスが用いた「宗主権」の概念については、インド総督のカーゾン卿が次のように述べている。
| チベットに対する清の宗主権というのは、条約上の方便です。 それはたんに政治上の言葉のあやであり、それが支持されてきたのは、両当事国にとって単に都合がよかったからに他なりません。 (中略) 実際のところ、ラサにいた清の2名のアンバンは、総督ではなく大使なのです。 |